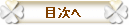私は私? 1
「君は、君に戻っただけじゃない?」
「戻った?」
「そう、変わったんじゃなくて、君が君でなくなったんじゃなくって、戻っただけ」
「戻ったなんて……そんな事」
「僕が僕であるように君は君なんだ」
彼の胸に向かって呟く私に彼は重ねて優しく言う。
彼の言葉はまるで魔法の呪文のよう。
この天邪鬼で自分の事しか信じない私が、彼に言われればそうかもしれないと何故か素直に納得してしまうんだから不思議。
「私は私?」
「違う?」
違うか?そう聞かれて違うとも正しいとも言えない。
私には全然分らないから……。
「昔の君はどんな子だった?」
唐突な質問に私は彼を見上げて首をかしげる。
彼の質問を疑問に思ってかしげたわけではなく、昔の自分を思い出そうとして思い出せないことに首をかしげたのだ。
昔の私……。
そんな事、今の今まで考えた事も無かった。
ううん、考えた事が無かったんじゃない、振り返ることが無かったんだ。
それは過ぎ去った時間だし、思い出なんてものに浸っている余裕は社会人になってからなかったから。
必死で働いて、必死で皆を抜かし、抜かれまいと努力してたんだもの。
振り返ろうとする事はいけない事。そんな気すらしていたから。
暫くだまって考えた振りをして、私は答えた。
「昔の私……思い出せないわ」
自然と体が考えた振りをさせるほど、私は、私の思考は過去を振り返るという行為を禁止しているようだった。
私の答えに彼はニッコリと薄いけれども優しい微笑を私に向けて、抱きしめていた腕をゆるめ、私から体を離した。
「自分の事なのに思い出せないの?」
初めて彼の言葉が私の頭に引っかかる。
確かに思い出せないのは私自身の事だけど「なのに」なんていわなくてもいいんじゃないか。
そんな風におもってしまい、私はフイッと顔を彼からそむけ、彼の体にしがみ付いていた腕を外す。
「……思い出せなくて悪かったわね」
不機嫌で、ムスッと答える私の頭の上からフフッと微笑む声が聞こえた。
怒っているとわかっているのに微笑まれて、私の機嫌は更に悪くなる。
静かに、怒っているけれど、ヒステリックになる事の無いように、私の表情は無になった。
ゆっくりと彼の体から後ずさる。
怒っている感情の中に何か寂しい気配もあったけれど、今の私はそれに気づきながらもその感情に蓋をした。
そっと、私の体に伸ばされてきた彼の右手を振り払って、何も言う事無く私は彼に背を向け、雑踏の中へと体を沈める。
冷たい風は私の顔を更に強張らせた。
暫く突き進んで、私はフト立ち止まり、背中に意識を集中した。
(もしかしたら……)
そんな馬鹿みたいに淡い期待に私の足が止まったのだ。
『本当に馬鹿ね』
私の中のもうひとりの私が呟く。
『なぁに?もしかして、彼が追いかけてきてくれるとでも思ったの?』
自分の中に響いたその声に私は俯いてきゅっと唇を噛み締めた。
『数回顔を合わせただけの彼が、アンタを追いかけてこなきゃいけない理由なんて無いじゃない。馬鹿じゃないの?男って言うのはそう言う事はしないわよ』
頭に木霊のように響き渡る自身の声が無性にイライラをつのらせ、私は眉間に皺を寄せて瞼を閉じる。
『本当は分ってるんでしょ?なんていったって経験済みじゃない。男は利用するものそれがアンタの信念だったじゃない』
「うるさい!!」
その場で叫んだ私の声は雑踏に木霊した。
一瞬雑踏がざわついたが、すぐにその波は普段通りに流れていく。
人ごみで叫んだ私も一瞬ハッとしたが、普段通りに流れていくその流れを眼にして、フッと小さな息をもらし、再び、私はその流れに逆らう事無く進んだ。
足取りは重たい。
川に流れている一枚の落ち葉のように、私はただ、周りの人に押されて動いている。
ぼんやりと動かしていただけだと思っていた足は、見事に私を自分の家に運んでくれた。
「習慣って怖いわね……」
自身の体に染み付いたその行動に苦笑が洩れる。
鍵を開けて入ってみれば、当然ながら真っ暗で、誰の出迎えもない、いつもの私の狭い部屋。
電気をつけなくたって、何がドコにあるのか分っているからつまづく事も無く、ベッドに座り込んだ。
体が重い、頭が動かない。
なのに、私の中の自分はいまだに悪態をついている。
彼女の声を聞きながら、私は彼女が自分であるのだと改めて確認していた。
 上へ
上へ
 "
"応援ヨロシクです♪